こんにちは。
先日、がん患者さんの妊孕性温存をテーマにした研修会に参加しました。
AYA世代のがん患者さんの妊孕性温存について、多職種からの講演が行われた研修会でした。
正直に言えば、妊孕性温存というテーマは、がん治療そのものに直接関わらない職種にとっては、「自分の専門とは少し距離がある」と感じやすい話題かもしれません。私自身も、セラピストという立場だったので、研修会に参加する前は、どこかそんな気持ちを持っていました。
しかし、講演を通して、がん治療だけでなく、妊孕性温存に関する支援体制が整えられてきていること、そして、特定の職種だけでなく、がん患者さんに関わるすべての医療者が知っておくべきテーマであると感じました。
研修会の終わり、ある医師の先生の閉会挨拶で語られた言葉が、強く印象に残りました。
先生の言葉が”希望”に感じました
妊孕性温存は、抗がん剤による、がん治療が始まる前に対応する場合が多く、早ければがんと診断されたごく早期の段階で患者さんに説明が行われることもあるそうです。
先生自身、がんのことを伝えて、動揺している患者さんに、妊孕性温存の話をするのは酷なことだと思っていたそうです。
そんな先生でしたが、がん治療後、無事にお子様を出産できた患者さんの言葉で思いが変わったようです。
「がんと診断されたときは、正直パニックになりました。その時に、妊孕性温存の話をしてくれたことが、私にとっては、治療がうまくいって、生きている未来を想像できて希望に感じたんです。」
先生は、その当時のことを穏やかな口調で語ってくれました。
“今”と”未来”の視点
治療やリハビリへの取り組み方や現在の生活環境、家屋状況、周囲のサポート体制など、
医療者は臨床において、「今この瞬間」の負担を考えることが多いように感じます。
一方、患者さんは「これから先の人生」を考えることもあると思います。
同じ言葉であっても、時間軸により変化するのだと思います。
反対に、「今」良かれと思って言った声かけであっても、「未来」という時間軸においては、
患者さんにとっては不安を募らせてしまう可能性もあります。
今回のように、医療者と患者さんの関係はその瞬間に完結してしまうものではありません。
医療者と患者さんの相互の語りが、
医療者あるいは患者さんの人生の中で、後から意味づけられることもあるのだと思います。
読んでいただきありがとうございました。
※本記事は研修会で共有されたエピソードをもとにしていますが、内容は個人が特定されないよう一部表現を調整しています。
T.A.

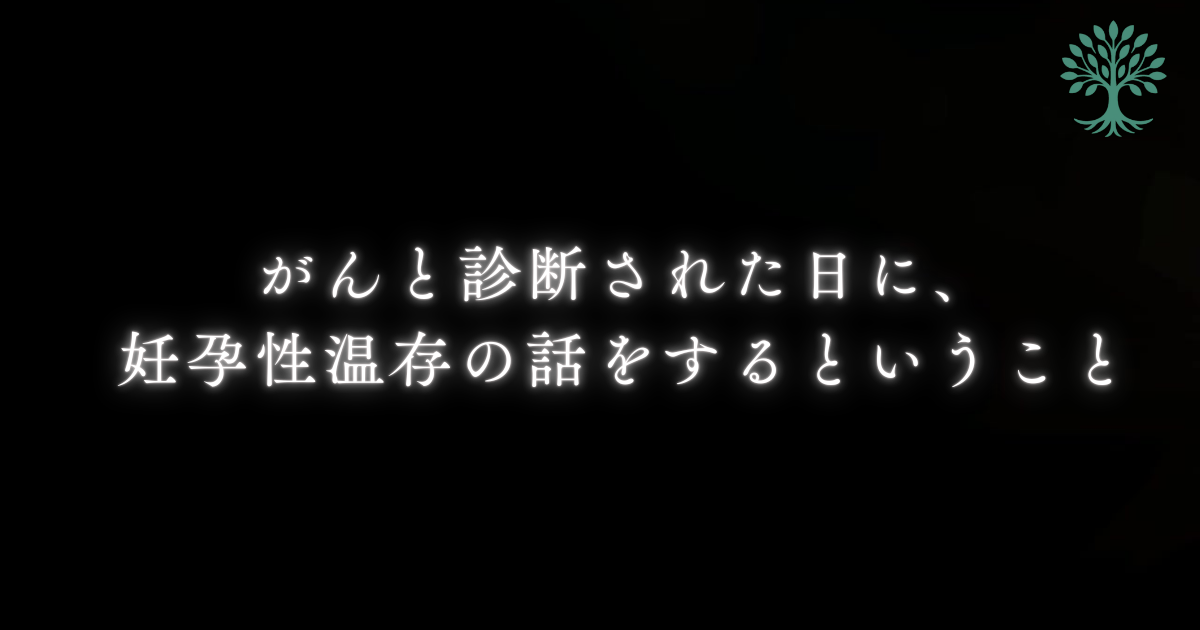


コメント