私は、理学療法士免許を取得し、急性期病院に勤めて十年を越えています。入職当初は、担当患者さんに初めて訪室するときなど、緊張して何と声を掛けたらよいのか分からず、悩んでいた記憶があります。入院後一日目からリハビリが始まることも多く、生活者から突如患者になったことを想像すると、「リハビリどころではないだろうに」と、よく思っていました。
臨床経験を重ねていくと、そのような緊張は少しずつ薄れていき、初回評価の場面では予後予測を意識するようになりました。カルテを確認し、病態や起こりうるリスク、キーパーソンなどの社会的背景を把握し、発言や態度に注意を払いながら目標を設定し、理学療法にあたります。それにかかる時間は、入職当時に比べて明らかに短くなりました。俯瞰してみると、どこか流れ作業のようで、冷たい理学療法士になっているようにも感じます。
一方で、流れ作業のような日々の中でも、患者さんはそれぞれ異なる背景を抱え、一喜一憂を繰り返しながら少しずつ前進しています。臨床業務に励んでいると、患者さんの回復を後押ししているだけでなく、いつの間にか自分自身が臨床業務を後押ししてもらっていると感じることがあります。
以前、中心性頚髄損傷を受傷した担当患者さんが、「努力してできないことはない。やると決めたら絶対やる」と話し、積極的にリハビリに取り組んでいました。セラピストであれば、この発言を聞いてどのように感じるでしょうか。脊髄障害は、受傷時点で身体機能の予後がある程度決まっていると言われています。セラピストの本心はさまざまであっても、返答は似通ったものになることが多いのではないでしょうか。「そうですね。リハビリを頑張って、少しずつできることを増やしていきましょう」。このような声かけです。
「少しずつ」あるいは「一つずつ」。筆者は、この言葉を無意識のうちに必ず添えているように感じています。前向きな声かけではありますが、臨床所見からある程度の見通しが立つがゆえに、回復の過程でどこかに壁があるだろうという事実を、心のどこかで拭いきれずにいるのだと思います。患者さんの前向きすぎる発言を、「自分の病態を理解できていないのではないか」と捉えてしまうこともあるかもしれません。しかし、筆者はそれは違うのではないかと感じています。その言葉は、患者さん自身が自分に言い聞かせている言葉なのではないでしょうか。
実際、その患者さんは言葉どおり懸命にリハビリに取り組んでいました。患者さんを待つ家族のために、「今まで、どんな困難も努力して一つずつ乗り越えてきた。たった一度の人生、楽しまないと損。先生、私頑張るよ」と語っていました。リハビリ中に起立性低血圧で意識を失ったり、膀胱直腸障害によって排尿がうまくいかず、回復が思うように進まないこともありました。そのようなときには暗い表情を見せることもありましたが、それでもへこたれることなく前に進んでいました。
もう一人、筆者の担当患者さんの中で、強く印象に残っている方がいます。その方は離島で一人暮らしをされており、病状が悪化し、絶望の淵に立たされるような状況でも、治療に対して前向きな姿勢を崩しませんでした。その方のリハビリを担当する中で、「この先どのような困難があっても、この方は何とかして大丈夫なのだろうな」と感じていました。
この患者さんの医療に対する姿勢に興味を持ち、インタビューを行った際、次のような言葉を聞きました。「頑張れない。頑張らない。やれるところまで。精一杯頑張るとか、命がけで頑張るとか、がむしゃらに頑張るとか、辛くて脂汗をかきながら頑張るようなことはしない。でも、自分の体が人と同じように戻っていくことに関しては、努力したいとは思う」。
リハビリは、手術や薬物治療とは異なり、患者さん自身の能動的な取り組みが重要になる場面が多いと感じています。先に紹介した二人の患者さんの言葉は異なりますが、どちらも積極的にリハビリに向き合っていました。
もちろん、すべての患者さんが同じようにリハビリに前向きになれるわけではありません。臨床において、セラピストが苦悩する場面の一つに、リハビリ拒否があります。「こんな体になってしまって、もう生きている意味がない」「体は動かしたくない。マッサージしてほしい」「もう十分生きたから、死んでもいい」。このような医療やリハビリに対する消極的な姿勢は、多くのセラピストが経験しているのではないでしょうか。
そのようなときに必要なのは、技術や声かけの工夫なのでしょうか。それとも、患者さんの前に立ち続ける理学療法士としての姿勢なのでしょうか。患者さんの気持ちが少しでも上向くような声かけを行い、離床につなげていく能力なのでしょうか。あるいは、あまり深く考えすぎず、患者さんが受け入れてくれるリハビリを淡々と行う力なのでしょうか。
なぜ理学療法士になったのか。その原点を、筆者はこれからも忘れずにいたいと思っています。拙い文章ではありますが、もやもやを語り合える場所は、患者さんだけでなく医療者にとっても必要なのではないでしょうか。「悩めるセラピストの場を、もっと広く提供したい」。それが、今の私の目標です。
※本エッセイは、ナラティブ研究会で検討した内容をもとに、個人情報保護の観点から背景や状況を一部改変して記しています。

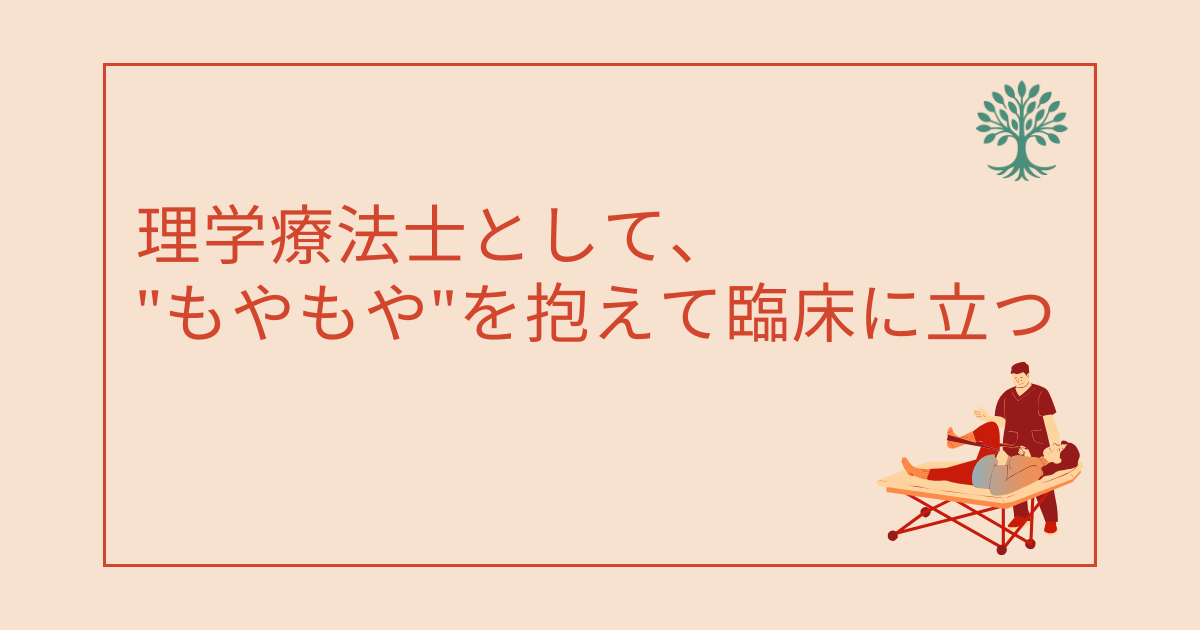


コメント